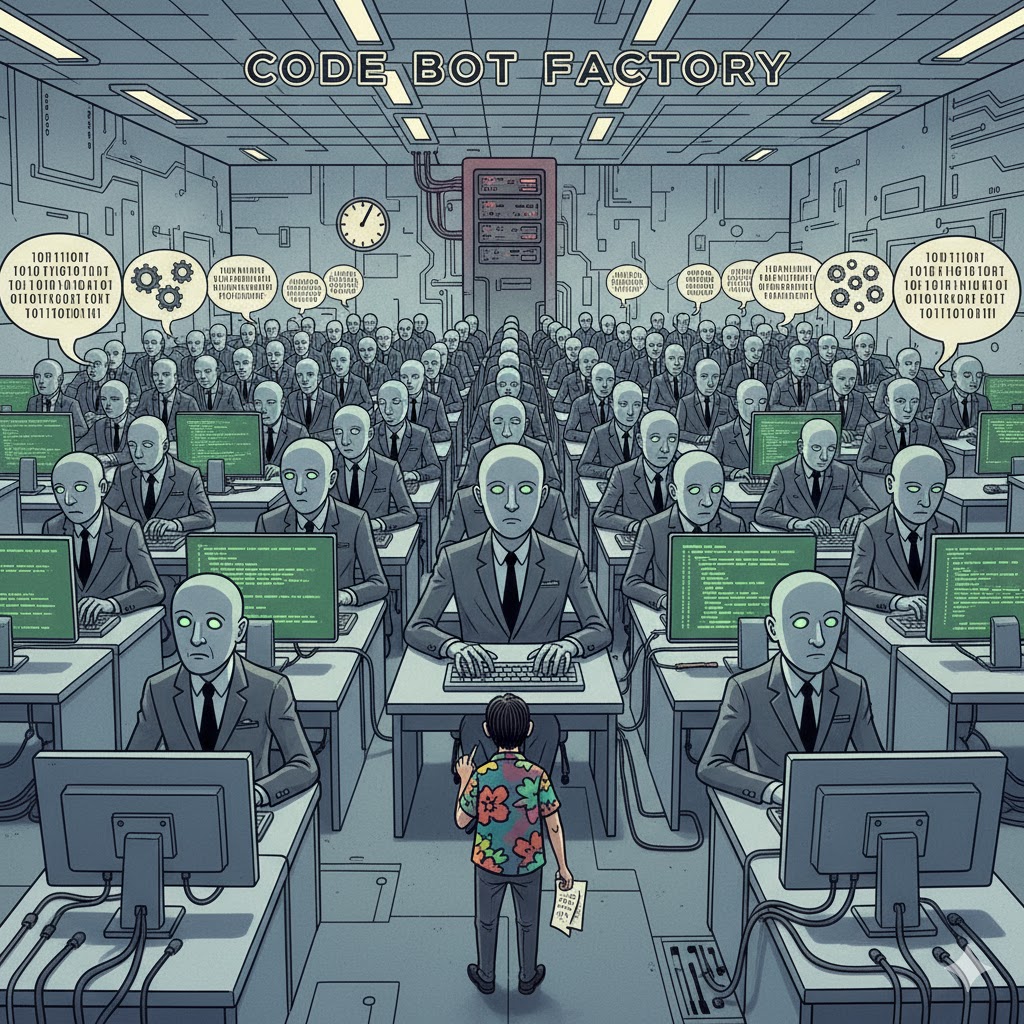AI駆動開発カンファレンスで確信した「終わりの始まり」
先日、「AI駆動開発カンファレンス」というイベントに参加しました。現地とオンラインを合わせ、3,000名もの参加者が集まったそうです。IT界隈でこれほどの盛り上がりを見せるコミュニティ・イベントは、最近では寡聞にして知りません。
これは、この分野への関心が非常に高いことは言うまでもないですが、それ以上に「技術の急速な発展にいち早くキャッチアップし、その動向を捉えておかないと大変なことになる」というエンジニアたちの焦りのような熱気を感じました。
カンファレンス主催者の冒頭の挨拶で、「AIが書くコードの品質も短期間のうちに劇的に向上した。もはや人間がコードを書く時代は終わりつつある」というメッセージがありました。システム開発の最前線にいる当事者(エンジニア)の言葉として、非常に重みのあるものでした。
これに続く、WindsurfやDevin、Factory.aiといった先進的なAI開発ツールのファウンダーやCEOたちによる基調講演も、この言葉を裏付ける内容でした。特に印象に残ったのは、「人間の役割は、AIが仕事をするためのReadiness(準備作業)になる」という指摘です。
コードを書くことやテストすることに労働力を提供する工数ビジネス(人月ビジネス)が、時間の問題で消滅することは、もはや疑う余地がありません。この「終わりの始まり」に、SIer、特に工数ビジネスへの依存度の高いSES事業者や下請事業者は、喫緊の課題として向きあう必要があると強く確信しました。
AIとクラウドがもたらす労働力の消失
この変革の核心は、AIが人間の「知的力仕事」を代替し始めている点にあります。AIがコードを生成し、テスト作業を自動化する「AI駆動開発」が、開発の前提となりつつあります。
米国の主要な調査会社であるGartner社のレポートでは、「2028年までに、企業のソフトウェアエンジニアの75%がAIコーディングアシスタントを使用するようになる」(2023年初頭時点では10%未満)と予測されています。これは単にツールを使うエンジニアが増えるという話ではなく、AIアシスタントを前提とした開発が標準になることを意味します。
もちろん、現状ではAIが生成するコードの品質が安定せず、それを検証する優秀なエンジニアに多大な負荷がかかるというボトルネックも存在します。しかし、これらの課題もやがて解決されるでしょう。
先日参加した「AI駆動開発カンファレンス」の熱気と、そこで発表された技術の進展スピードを鑑みるに、このGartnerの予測(2028年)すら前倒しになり、流れはさらに加速するのではないかと私は感じています。つまり、コードの生成やテストに必要な従来の「労働力」は、私たちが想定するよりもはるかに短期間のうちに劇的に減少することを覚悟しておく必要があるのです。
このトレンドに適応し、生成AIやAI駆動開発を使いこなすSIerは生産性を飛躍的に高める一方で、そうでないSIerとの格差は広がり、やがては市場からの淘汰圧にさらされることになります。
さらに、クラウドサービスの充実と、マイクロサービスやコンテナといった「クラウド・ネイティブ」技術の普及も見逃せません。これらを組み合わせることで、従来のようにゼロからコードを書き、テストを行うといった労働集約的な作業そのものが減少しつつあります。
人月ビジネスモデルの終焉と下請け構造の瓦解
このような一連のトレンドは、SIerの伝統的なビジネスモデル、すなわち「労働力(工数)を提供し、その対価として収益を得る」という人月ビジネスの基盤を根本から揺るがしています。
技術の進化によって「労働力」そのものが必要とされなくなれば、人月ビジネスが成り立なくなるのは必然的な流れです。特に、エンジニアの労働力を客先に提供することに依存するSES(システムエンジニアリングサービス)ビジネスは、深刻な影響を免れないでしょう。
この影響は、SESビジネスだけに留まりません。都市部の大手SIerの下請けとして、コード生成やテスト作業を長年請負ってきた地方のIT事業者にとっても、事態は深刻です。
その背景には、大きく二つの構造変化があります。
1. 大手SIerのビジネスモデル変革
一つ目は、発注元である大手IT事業者自身の変革です。彼らは、AI駆動開発やクラウドを前提とした、より付加価値の高い「オファリング・ビジネス」へと急速にシフトしています。同時に、自社のコンサルティングビジネスを拡大させ、上流工程から顧客を自社の戦略やプラットフォームへと導くシナリオを描いており、下請企業の労働力に依存する体制から脱却し始めています。
2. ユーザー企業による「内製化」の拡大
二つ目は、SIerの最終顧客であるユーザー企業側が「内製化」に大きく舵を切り始めている点です。不確実性が常態化する現代において、企業が生き残るために不可欠な「俊敏性」を獲得するには、外注に頼る体制は足枷となります。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発行する「DX白書」などの調査でも、DXを推進する企業の多くが内製化に取り組む姿勢を強めています。
ユーザー企業の内製化が進めば、大手SIerへの発注は減少します。結果として、下請け企業に仕事が回らないようになり、長年日本のIT産業を支えてきた「元請・下請」という人月ビジネスの構造そのものが瓦解へと向かっているのです。
では、どうすればいいのか
このような厳しい状況下で、私たちは何を考え、どう行動すればよいのでしょうか。
端的に言えば、人月に依存する「労働力」で稼ぐビジネスから、「技術力」で稼ぐビジネスへの転換を急ぐ必要があります。
「そんなことは分かっているが、どうすればいいのかがわからない。」
そんな声が聞こえてきそうです。確かに、既存の人材をそこに転換することは容易ではありません。
当然ながら痛みを伴う変革が必要ですが、できない話ではないと、私は考えています。そのシナリオの柱は「時間差の利用」と「自律的組織への転換」です。
1. 時間差の利用:AI移行期に生産性を極大化する
まず「時間差の利用」についてです。
短期間のうちに、コード生成やテスト作業は「技術的には」AI駆動開発ツールに置き換わるでしょう。しかし、ユーザー企業もSIerも、既存システムの複雑さや検証体制の確立の問題から、この変化に明日から即応することは容易ではありません。なぜなら、単にツールを導入すれば済む話ではなく、長年かけて複雑化した既存システムとの連携、AIが生成したコードの品質を担保する新たな検証プロセスの構築、そして何より、従来の開発プロセスに最適化された組織文化や契約形態そのものを見直す必要があるからです。
この「技術的な可能」と「組織的な受容」の間に生まれる「時間差」こそが、変革を目指す事業者にとってのチャンスとなります。
この「時間差」戦略を担うのは、特に高度なスキルを持つベテランのエンジニアであるべきです。なぜなら、彼らはAIが生成したコードの品質を瞬時に見抜き、その文脈(パフォーマンスや保守性)まで考慮した最適な指示を出せる「判断軸」を持っているからです。彼らがCursorやWindsurfのような、使い慣れたIDE(統合開発環境)をベースとしたAI駆動開発ツールを徹底的に駆使することで、AIの能力を最大限に引き出すことができます。これらはベテランにとって学習コストが低く、スキル習得が容易であるため、その能力を即座に生産性の向上に結びつけ、文字通り「何倍」にも高めることが可能になるのです。そして、少ない人数で多くの案件を短期間のうちにこなし、新しい技術へのキャッチアップが遅れているユーザー企業のニーズを取り込み、高収益を維持することを目指すのです。
しかし、これはあくまで移行期の戦術です。AIが完全に普及すると、この時間差の戦略的効果は失われます。ここで言う「AIが完全に普及」するとは、単にAIアシスタントの使用率が上がるという意味ではありません。以下の3つの変化が起こると考えられます。
- DevinやFactory.aiに代表される、自然言語で目標を与えるだけで自律的にコードを生成しテストまで実行する「AIエージェント」が、機能や性能を向上させ、普及すること。
- XAI(説明可能なAI)の技術が進歩し、AI自身がコードの意図をリバースエンジニアリングし、自律的にバグの修正や改善を行える能力を持つこと。
- AI開発プラットフォーム自体がコモディティ化し、あらゆる開発プロセスにAIが標準で組み込まれること。
これらが現実になれば、ベテランエンジニアが介在する「時間差」は消滅します。昨日のカンファレンスで示された技術の進展スピードを鑑みるに、この「時間差」で稼げる時間的余裕は、我々が想定するよりもずっと短い可能性があり、対策を急ぐ必要があります。
従って、より本質的な変革が、次の「自律的組織への転換」です。
2. 自律的組織への転換:真の「技術力」を育む
本質的な変革とは、収益の源泉を「労働力」から真の「技術力」へとシフトさせることです。
ここで言う「技術力」とは、単にAIやクラウドといった高度なテクノロジーを使いこなすスキルだけを指すのではありません。それ以上に重要なのは、ビジネスの課題をテクノロジーによってどう解決すれば良いかを構想・提案し、それを確実に実現できる能力です。
AIの登場により、エンジニアに求められるのは「コードを書く」という知的力仕事ではなくなりました。AIの生成物を単に受け入れるのではなく、それを批評・改善できる高度な「目利き」となり、知的力仕事から解放された時間を、この「テクノロジーを前提としたビジネス構想力」の発揮に充てること。この『構想力』と『目利き』こそが、これからのエンジニアの提供すべき中核的な価値となります。
この「構想力」は、コンピュータサイエンスなどの「原理原則」という土台なしには育ちません。AIが提示するコードの良し悪しを判断する「判断軸」の有無が、AIを使いこなす者とAIに振り回される者との格差を生むのです。
しかし、このような高度な「判断軸」と「構想力」を兼ね備えた人材を、旧来のビジネスセンスや経験値しか持たない人間が育てることは困難です。
だからこそ、経営者は彼らに明確なミッションやビジョンを示し、その実現方法を現場が自ら考え行動できる「自律的な取り組みを促す組織」を作ることが不可欠になります。新しい時代のテクノロジーやメソドロジーに自発的に挑戦したいと考える人材にチャンスを提供し、積極的に支援するためにも、組織や報酬の制度も従来のやり方にこだわらず、ジョブ型やポスティング制度などをうまく使い、新しいことに取り組もうとする人材を生み出し、挑戦を支援していくべきです。
この「自律的組織への転換」については、以下の記事が、参考になると思います。
おわりに
もちろん、以上のような取り組みは「簡単ではない」という人もいるでしょう。長年の慣習を変え、既存のビジネスのやり方を否定することには痛みが伴います。
しかし、技術革新によって自分たちの事業が存続できなくなった後で、どうやって生きていくのかをゼロから模索するほうが、よほど「簡単ではない」未来ではないでしょうか。
変化のスピードが加速度を増すなか、わずかな躊躇が圧倒的な価値の格差となってしまいます。私たちは皆、この3つを自問し続けなければならない時代に生きているのです。
- あなたは、時代の趨勢を見極めようとしていますか?
- あなたは、自分たちの土台が、これまでと変わってしまったことに目をつむっていませんか?
- あなたは、労働力を売る『昨日』から脱却し、技術力で『明日』を構想する『問い』を発し続けていますか?
「システムインテグレーション革命」出版!
AI前提の世の中になろうとしている今、SIビジネスもまたAI前提に舵を切らなくてはなりません。しかし、どこに向かって、どのように舵を切ればいいのでしょうか。
本書は、「システムインテグレーション崩壊」、「システムインテグレーション再生の戦略」に続く第三弾としてとして。AIの大波を乗り越えるシナリオを描いています。是非、手に取ってご覧下さい。